
こんにちは
だまブログ管理人のだまです。
あなたにとって「あの頃は自分らしかった」「充実してた」という時期はいつですか?
最近わたしは、転職活動の合間に自己理解を深める中で、そんな問いを自分に投げかけてみました。
そして思い出した「あの頃」。
その共通点に、ハッとしたんです。
それは——
「自分で決めて、自分で責任を負って生きていたとき」
たったそれだけ。でも、ものすごく自由で、ものすごく“自分”だった。
今回はそんな日々のことを書いていきたいと思います。
この記事は、このような方におすすめです
- 子どもを持たないことに後ろめたさを感じている女性
- 周囲の期待に応えすぎて、自分の“欲求”や“本音”がわからなくなっている女性
- 子どもや肩書きなど“社会的な意味づけ”がないと、自分の価値を感じにくい女性
充実していた時期を探ったら見えてきたもの
振り返ると、充実していたなと思える時期は人生に2回ありました。
①21歳のときのニュージーランド・ワーホリ生活。
②36歳で実家を出て一人暮らしを始めた時期。
(え、結婚生活は?と思ったあなた、大丈夫 わたしも思いましたが、それについてはコメントを控えさせてください)
この2回に共通していたのは、
「衣・食・住を自分で決め、自分の足で立っていた」ということ。
生活も仕事も理想とはかけ離れていたけれど、わたしの中には確かに“自由”があったんです。
“自由”って、実はすごく地味で静かなものだった
ワーホリで住んでいたNZでは、安宿でベットのダニに悩まされながら、 チーズとパンばっかり食べて10kg増量。
仕事は、トイレ掃除と皿洗い、近所でベビーシッター。
最高のキャリアでもなく、最適な生活環境でもなく、 人間関係もまあ、良い人もいれば変な人もいて。
でも、
「どこに泊まるか、何を食べるか、誰と関わるか」
それを全部自分で決めて、失敗しても全部自己責任で、
自分で決めたことで人生が形作られていた。
最初こそ、慣れない環境に押しつぶされそうになったけど、
慣れたあとはその生活が楽しくてしかたなくなった。
誰の期待も評価も気にしなくていい。
そこにいるために誰の許可も必要ない。
わたしの決断基準に他人の目がなくなったことで、心が自由になっていたんです。
一方、36歳で実家を出て一人暮らししたとき。
あの頃は仕事もプライべートも散々で、心がバッキバキに折れて、実家で過ごすのがしんどくて、
逃げるように実家を出て借りた小さなアパート。
自分の好きなように部屋を整えて、好きな物だけ好きな時間に食べて・・・
その「一個一個、自分で選んでやってる感」が、何よりも心を落ち着かせてくれた。
この地味だけどすごく深い安心感を、改めて手に入れることができた。
他人の期待に応える人生の末路
物心ついたころから、わたしは他人の期待に応えることで、自分の存在意義を保ってきた。
家庭でも、仕事でも、「他人の期待を察して応えること」に自分をエネルギーを注いできた。
自分の本当の気持ちより、「その場を乗り切ること」が大事になってた。
結果、何をするにも「これで(わたしがここにいることを)認めてくれるだろう」っていう基準で動くようになってた。
自分の体も心も、ギュッと縮こまって、 まるで親しみやすい仮面をかぶった「偽物の自分」を演じている日々。
結婚前は親の顔色や期待を察して、それに応えていたし、
結婚後は夫の顔色や期待を察して、それに応えている。
でも、そんな生き方ではいつか限界が来るんですよね。
だってこの生き方じゃ、”自分”はどこにもいなくなってしまうから。
他人の期待に応えている限り、自分のニーズや欲求は後回しにされ続ける。
そんな「自己犠牲」的な生き方では、
自分の人生を生きること、
自分を満たせるわけがなかったんですよね。
わたしはずっと「他人の役に立てれば、わたしにも価値がある」って思ってた。
だから誰かに頼られると、断れなかったし、期待以上に対応していた。
でもそれって、裏を返すと「わたしはありのままじゃ価値がない」って思い込みに縛られてるってこと。
でもわたしが本当に満たされていたのは、 「誰かの期待に応えて自分を評価してもらったとき」じゃなくて、 「他人の期待なんか気にせず自分の欲求に素直に生きてたとき」だったんです。
我慢じゃなく、“線引き”で共に生きる
わたしは昔から極端に“他人の期待に応えすぎる”クセがあるんです。
親の期待、上司の期待、夫の期待。
察して動くのがうまいけど、それって…
自分を後回しにする癖にもなってた。
最近ようやく思うようになりました。
もうそろそろ、「極端に合わせすぎる自分」は卒業したい。
でも、だからといって
「じゃあもう誰とも関わらず一人で生きる!」みたいな極端さも…それはそれでしんどい。
じゃあ、どうやって他人と一緒に暮らしていけばいいんだろう?
たぶん必要なのは——
我慢じゃなくて、“線引き”。
共生って、全部を譲ることじゃなくて、
「ここから先はしんどい」って、ちゃんと自分に気づいて、言葉にすること。
・今日は本当は誰にも会いたくなかった
・もっと優しくしてほしかった
・無理に笑ってたけど、ほんとは泣きたかった
そんな“ほんとは”を置き去りにすると、
あとから心が爆発するんですよね。
(わたしもよくやる。「勝手に我慢して、勝手にキレる人」)
だから、最近はこう思ってます。
「苦しいかも」と感じたら、それは“心が出してくれてるサイン”。
わたしは「違和感」を感じるたび、こう問いかけるようにしてる。
「これ、ほんとにわたしが望んでること?」
「誰かの期待に応えてるだけじゃない?」
心の違和感は、“本当の欲求に戻るための手がかり”なのかもしれない。
だから、無視しない。なかったことにしない。
自分の心に従って、それを言葉にして相手に伝える。
怖くても、少しずつ。
本当の共生って、お互いの「心地よい距離感」を探る作業なのかもしれません。
「察してくれない相手が悪い」じゃなくて、
「わたしが、ちゃんと自分の境界線を伝える」って覚悟を持つこと。
それが、わたしがこれから築いていきたい、やさしい共生のかたちです。
■人生の充実に「母である」ことは必須項目ではない
子どもがいなくても、自分の人生にちゃんと“自由”と“充実”を感じられる瞬間があった。
それは、誰かの期待から降りたとき。
「母になるべき」「女性は家庭を持ってなんぼ」みたいな、
時代遅れのテンプレから脱出したとき。
わたしの人生は、わたしが選んだ衣・食・住でできてる。
自分の足で立ってる。
結局、わたしにとっては充実した人生に必要だったのは、「自分で立つ」ことだった。
「母」であることは必要ではなかった。
もちろん、わたしは「母」ではないから、「母」であるバージョンの人生充実度を知らない。
だから分からない。
でも、分からないことは分からないまま、ほっとけばいいんじゃないか。
たとえ誰にも必要とされてないように感じる日があっても、
自分が自分を必要としてれば、それで生きていける。
不妊治療の後の人生って、空白じゃない。
手に入らなかったからこそ、やっと“わたしの本音”に向き合える時間が始まるんですよね。
■まとめ:「自由の中に“自分”がいる」
他人の目や期待に応えてばかりの人生を、もうやめよう。
わたしたちは、「ちゃんとしなきゃ」の呪いにかかりすぎてる。
母じゃなくても、妻じゃなくても、会社員じゃなくても、
立派な肩書きがなくても、わたしは“わたし”として生きていい。
わたしがわたしに「OK」を出せたら、それがすべての始まり。
あなたにも聞きたい。
・その価値観、ほんとに自分のもの?
・人に満足してもらうためだけに、がんばってない?
・自分の心が満たされてないのに、誰かの心ばかり満たそうとしてない?
今のあなたが、何も成し遂げてなくても。
部屋でゴロゴロしてても。
ごはんを適当に済ませても。
それでも十分、あなたは生きてる。
大丈夫。
人生のハンドルは、他人に預けるな。
自由は、「自分で決める力」そのもの。
そして「自分を大事にする覚悟」そのもの。
好きに生きろ。
他人と暮らすのもいい、でも、我慢はするな。
心の違和感に正直に、自分の欲求に忠実に、これからの人生”わたし”のままで生きていきたい。
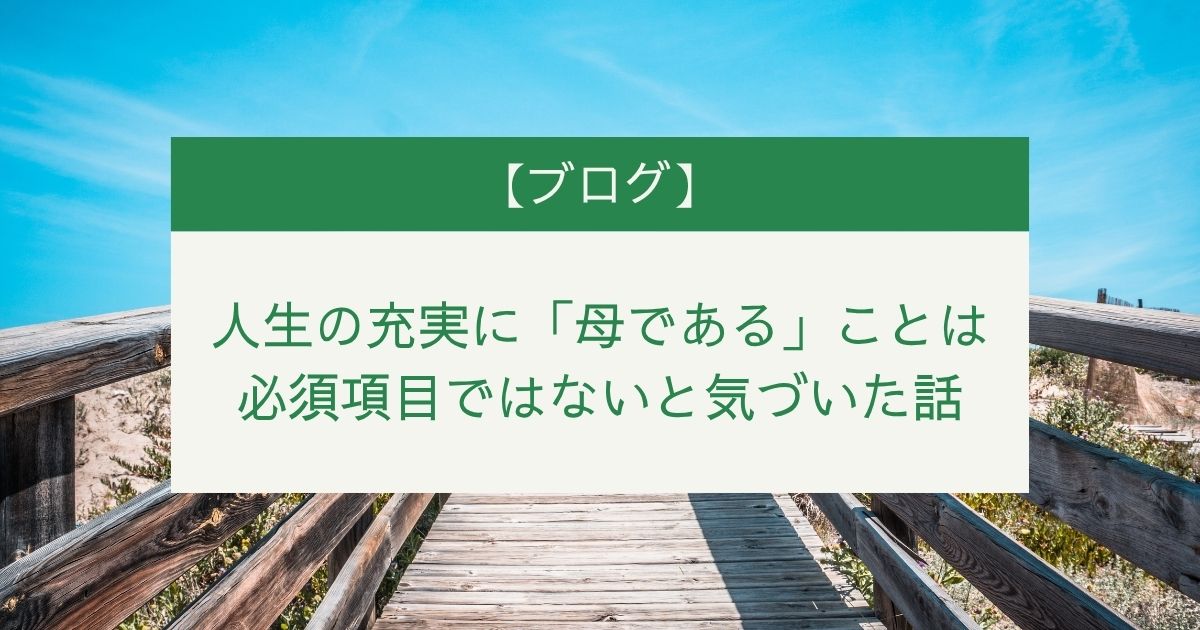
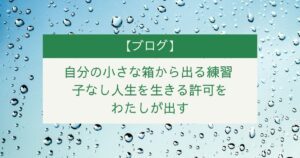
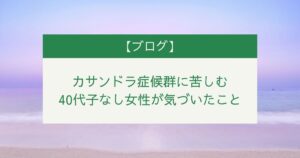
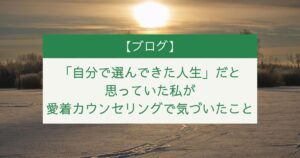
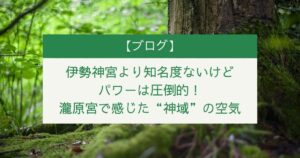
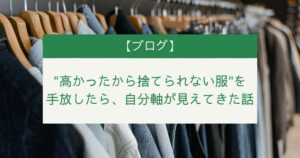
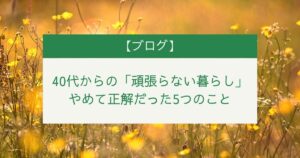
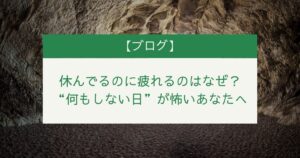
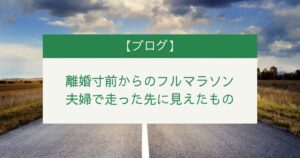
コメント