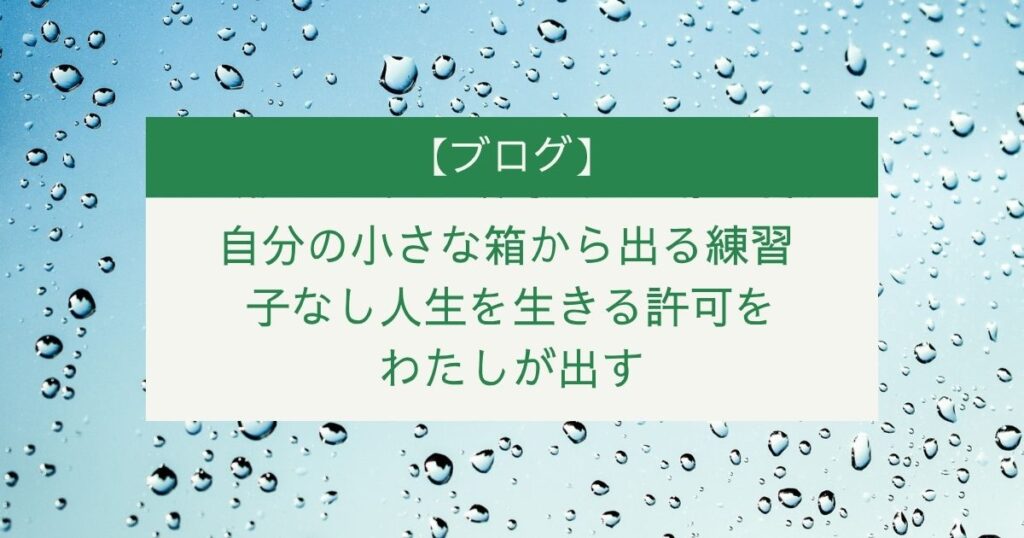

こんにちは
だまブログ管理人のだまです。
あなたは、自分の中に「思い込み」をたくさん持っていませんか?
「役に立たないと愛されない」
「子どもがいない私は不完全だ」
そんな自分の中の思い込みのせいで、
なんだか息が詰まって、心が狭い場所に押し込められているような気がする。
最近わたしは、そんな思い込み(認知の歪み)を「心の箱に入っている」と表現する本に出会いました。
「自分の小さな箱から脱出する方法」という本です。
この本を読んで、
「人は箱に入るとき、自分や他人をモノのように扱ってしまう」という言葉に、ギクッとしました。
まさに、自分を守るために他人を攻撃しモノのように扱ってきた覚えがあったからです。
今回は、子どもを持たない人生を生きる中で、
私がどれだけたくさんの箱に閉じこもっていたか、そしてどうやって少しずつ出ようとしているか、そのことをお話ししたいと思います。
この記事は、このような方におすすめです
- 子どもを持たないことに後ろめたさを感じている女性
- 他人の期待や評価で自分の価値を決めてしまう人
- 自分を責め続けて生きることに疲れている人
◆ わたしを閉じ込めてきた「心の箱」


この本で言う「箱」とは、
自分を正当化するために他人を責める心の状態のこと。自分の本心にウソをついている状態のこと。(自己欺瞞という)
箱(思い込み=認知の歪み)に入った状態が長くなると、いずれ箱に入っている状態が通常になり、歪んだ認知のまま人格が形成されていってしまう。
本を読んで気づいたけど、わたしの入っている箱は、けっこう大きくて複数あった。
箱①:弱さを見せると仲間外れにされて見捨てられる
箱②:役に立たなければ愛されない
箱③:子どもがいない女性は不完全
箱①②に関しては、子どもの頃に形成され、箱③に関しては結婚後に形成されました。
何か傷つく出来頃があり、また自分に不都合な出来事があって、そのとき自分を守る(正当化するために)、周りの人をモノ扱いし攻撃的に接してきたと思います。
夫に対しても思えば同じでした。
「寂しい」
「ありのままを愛して」
と結婚当初は素直に言っていたのに、応えてくれないことに傷つき、代わりに責めるようになっていきました。
「なんで分かってくれないの!」
「なんで寄り添ってくれないの!」
「わたしは悪くない!」
◆ 子なしであることが「箱」になる


この社会は、子どもを産んだ人と産まない人の間に、見えない溝をつくりがちだと思いませんか。
「子どもがいないと生きがいがない」
「子なし女性は自分のことばかりで精神的に未熟」
気づけばわたしも、
「母になった人は勝ち組、わたしは負け組であり不完全な存在」
と自分をジャッジする箱を作って自分を責めていました。
本にはこう書いてありました。
「箱に入るとき、人は相手をモノのように見る」
それは他人だけじゃなく、自分にも同じことが言えるんです。
わたしは、自分のことをずっと「不完全な存在」というモノ扱いしていました。
そしてそんな自分を守るために、他者を落として攻撃して、自分を保ってきたのです。
◆ 他人に許可を預け続けた生き方


思えば、わたしはずっと「わたしがこの世に存在する許可を他人に預ける」生き方をしてきたんだと思うんですよね。
「あなたはそのままで大丈夫だよ」
「あなたはそのままで価値があるよ」
ってずっと言われたかった。
そしてそれを聞きたい人から、それを聞きたい時に言われなかった。
夫に、親に、社会に。
でも、もうさすがに気づいたんです。
それを言って欲しい人から、その言葉を聞ける日はこの先来ないだろうこと。
もうわたしは充分苦しんだし、他人の許可を待つ時間は終わりにしていい。
それは絶望ではなく、ようやく自分で自分に許可を出す(他人軸から自分軸に戻す)覚悟ができたんだと思います。
◆ 自分に自分で許可を出す


「自分の小さな箱から脱出する方法」には、
「今、自分が箱に入っている」と気づけたらもう箱の外に出ている、と書いてありました。
わたしは、自分が箱に入っていたことに気づくことができたけど、
時間が経つとまた無意識に箱の中に戻っていて、歪んだ認知で世界を見ている時もあり、常に箱の外に出て生きることは難しいと感じています。
でも、考えてみればそりゃそうですよね。
物心ついたときから、ゆっくりと形成された私の認知の歪みが、そう簡単に外れるわけがない。
だけど、この箱(認知の歪み)は全部、自分を傷つける(と思い込んでいる)世界から自分を守るための箱。
今までは自分を守るために必要だった箱なんです。
でも今はもうその箱から出てもいいと思っている。
いや、むしろ出たい。
自分や他者や世界を信頼したい。感謝したい。
その箱の中から見ていると、世界も人もモノのまま。怖い世界のままなんです。
そしてその箱から出たら、世界も人もそこまで怖い存在ではなかった、という事に気づいたんです。
あの人はわたしを攻撃していた訳ではなかった。
あの人はわたしをナメていた訳ではなかった。
わたしの認知の歪みが、世界を歪めていたんだ…!
と解釈できる過去の出来事もありました。
もちろん、実際に怖い人も怖い場所もあります。
でも箱から出ても、怖い人や場所を避ける知識や知恵、経験がもう自分の中にあると今は思える。
だから、箱の中から自分の権利を叫ぶ人生はやめて、もうわたしの存在価値に関する許可を、他人に預ける人生は手放したい。
「子どもがいないあなたも、寂しがりのあなたも、弱いあなたも、そのままで愛される権利があるし、そのままで生きていい」
それが、わたしがわたしに出す許可です。
◆ 箱から出るために練習していること


今わたしが、箱からちょっとずつ出るために練習していることを紹介します。
🌿 1. 正直に気持ちを伝える
「わたし、本当はすごく寂しい」
「不安でたまらないときがある」
「子どもを持たない自分に罪悪感を感じることがある」
これを心の中でごまかさずに声に出す。
信頼できる人に話すか、ノートに書く。
言葉にすると、心が少し整理されます。
相手の反応が期待外れでも、気にしない。
🌿 2. 自分を「人」として見る
「母でも妻でも、誰かの役でもなく、ただの人間でいい」
「わたしはある部分は有能で、ある部分は無能で、人間はみんな同じ」
そう言い聞かせる。
肩書きや役割でジャッジしそうになったら、
「わたしはわたし、みんなも同じ」とつぶやく。
🌿 3. また箱に戻っても責めない
気づけばまた
「夫がこうしてくれないから苦しい」
「やっぱりわたしは欠けてる」
そう思うときが来る。
そのときは
「ほらまた箱に入ってる」
と自分に声をかける。
笑って箱に入っている自分を許す。
怖かっただけなんだ、と弱い自分を認める。
🌿 4. 自分に愛していると声をかける
「I love you」
「I see you」
「I accept you just as you are」
毎日、鏡を見てこの言葉を自分に言うアファメーションをやっています。
日本語で言わないのはなんか恥ずかしいからw
わたしが参考にしているアファメーション動画はこちら↓
🌿 5. 小さな「NO」を練習する
人の期待を察知して、その期待に応えすぎてしまう自分に気づいたら、
小さな「NO」を言ってみる。
「今日は行けません」
「それはやりたくない」
「もう帰りたい」
自分の気持ちや体調を優先して、他人の期待をかわす練習。
🌿 6. 孤独を怖がらない練習
一人の夜が寂しくなったら、
「これはわたしにしか味わえない時間」と思う。
湯たんぽを抱いて、
好きな音楽をかけて、
「ああ、いま孤独だね」と確認するだけでいい。
でも無理に他人といなくてもいい。
🌿 7. 「まあ、いっか」を口ぐせにする
完璧にできなくても、また箱に戻っても、
「まあ、いっか」と言う。
この言葉だけで、緊張がすこし緩む。
完璧でなくても、ポンコツでもいい。
ちゃんとしてなくてもいい。
🌿 8. 感謝メモを書く
1つ嫌なことがあると、その気持ちに飲み込まれて感謝を忘れがちになる。
だから、小さな感謝ができる心を忘れないようにメモに残す。
この世のすべては当たり前ではない。
全部正解・全部奇跡だと思った方が人生が輝く。
◆ まとめ 〜子なし人生に「それもあり」と言う〜
この本に出会って、わたしは思いました。
子どもを持たない人生は、確かに孤独の瞬間が多いし、世間では少数派です。
でも、だからってそれは「何かが欠けた人生」ではない。
他人に預けていたわたしの存在への許可証を、もう絶対に誰にも渡さない。
「このままで生きていいよ」「足りないものなんかない」って、何度でも自分に言ってあげたい。
わたしがこの世に存在するために自分以外の許可なんて、本当は必要ない。
もし、あなたも同じ箱に閉じこもっているなら
一緒に言いませんか?
「わたしはわたしを愛してる」
「わたしはわたしを見ている」
「ありのままのわたしをわたしは受け入れる」
その小さな箱から出て、一緒に自由な世界に飛び立ちませんか?
大丈夫。
本も読んでもないのに「もしかして自分も箱に入ってるかも?」と思っているあなたは、すでに箱から出ている可能性があります。
センスめっちゃあります。
最後まで読んでくれてありがとうございました。
最後に、この本を紹介してくれた、あがり症日本代表のりゅうさんへ感謝を込めて
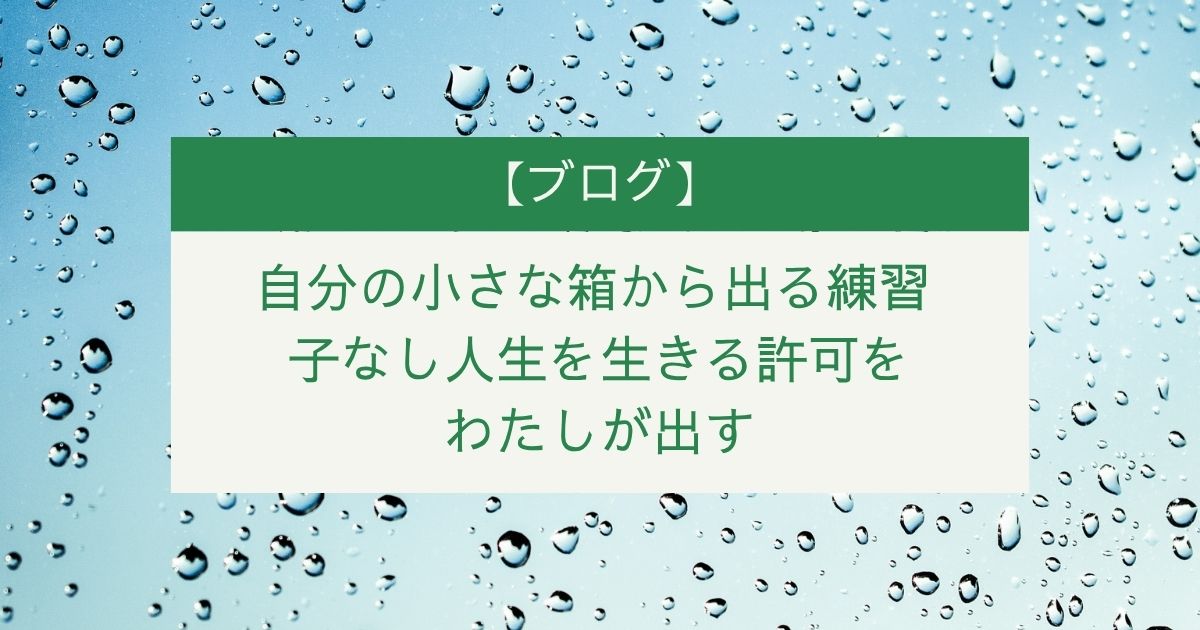
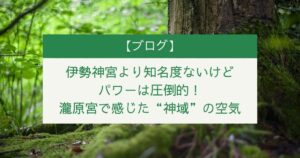
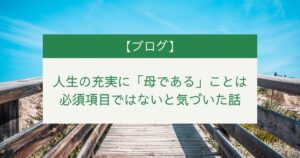
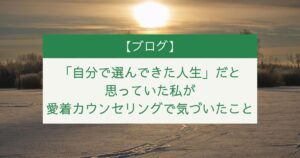
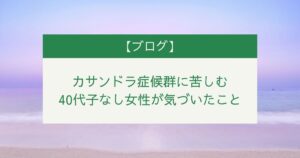
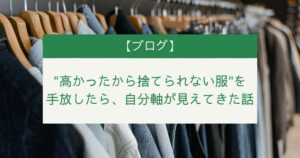
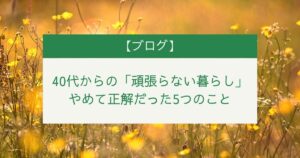
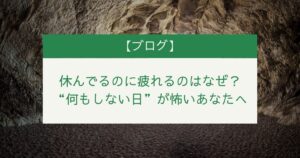
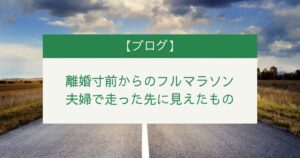
コメント